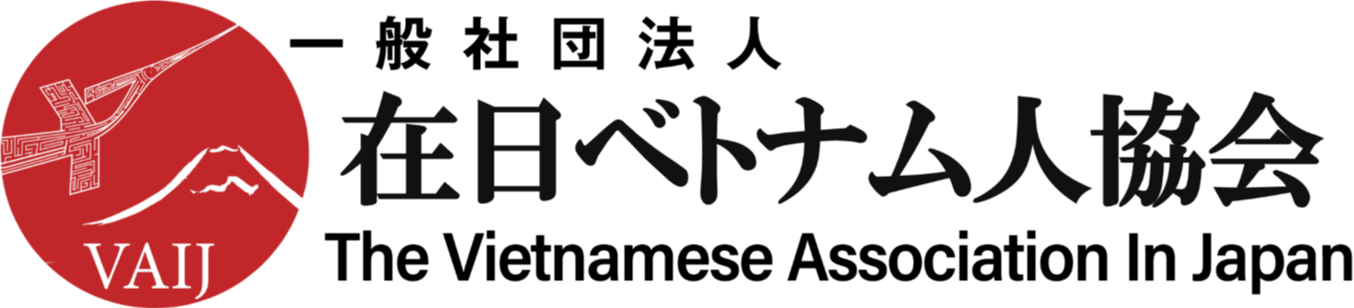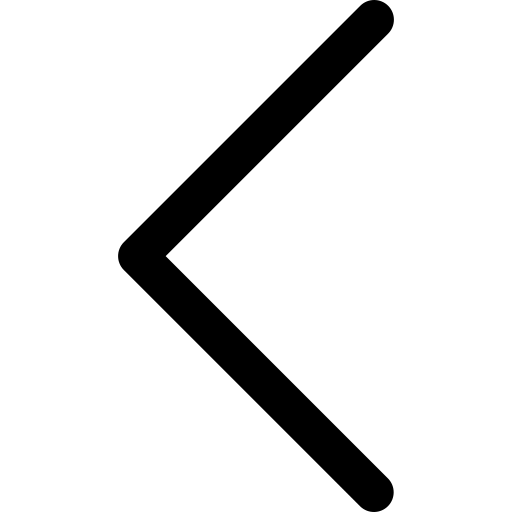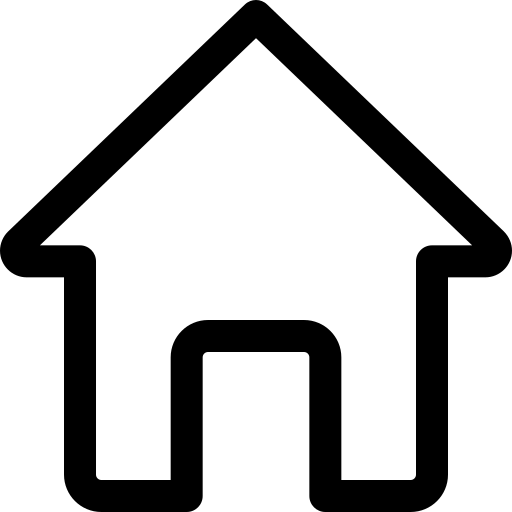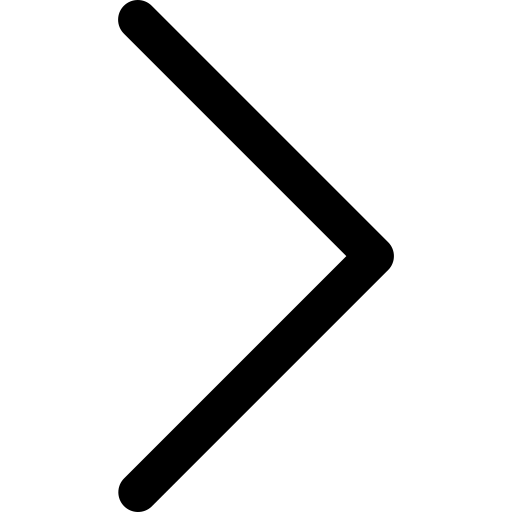旅行・グルメ
日本料理レシピ_part7:「ゴーヤーのかき揚げ」と「豚肉と大根の煮もの」

比較的安い材料で作れるおいしい日本料理を紹介するシリーズです。今回は、ベトナム人にもなじみ深いゴーヤーを使った「かき揚げ」と、簡単に作れるメインディッデュ「豚肉と大根の煮物」を紹介します。日本に長く住むベトナム人女性がかき揚げを作り、料理の得意な日本人記者が煮物を料理しました。
ゴーヤーのかき揚げ

ニガウリ(ゴーヤー)はベトナム人にとって身近な夏野菜の一つで、日本でもさまざまな料理に使われています。日本で一番ポピュラーなゴーヤー料理は、豚肉や卵、豆腐などと一緒に炒(いた)める沖縄料理で「ゴーヤーチャンプルー」です。
◆ゴーヤーの主な栄養素
ゴーヤーには独特の苦みがありま、その成分は「モモルデシン」と言います。この成分は食欲を増進する作用があるうえ、血糖値を下げる効果も期待されています。
また、ゴーヤーの「チャランチン」いう成分にも同じように血糖値を下げる効果があり、さらにコレステロールも低下させるそうです。
このほか、βカロテンやビタミンCをはじめ各種ビタミン類も豊富に含んでいます。いずれも油との相性が良いので、炒め物などにして食べると、効率よく吸収されます。
それでは、ゴーヤーを使ったかき揚(あ)げの作り方を紹介します。
材料 (2〜3人分)

1. タマネギ:中1個 (約100 g)
2. ニンジン:50 g
3. ゴーヤー:100 g
4. 乾燥サクラエビ:10 g
5. 天ぷら粉:約50 g
6. 氷入り水:150㏄
作り方


- 1タマネギは薄くスライスし、ニンジンは千切りにします。ゴーヤーは縦に半分に切ってから中のわたを取り除き、薄くスライスします。
- 21の材料とてんぷら粉をボールに入れます。


- 3材料をはしでかき混ぜ、てんぷら粉を野菜全体になじませます。
- 43に冷水を入れ、はしで軽く混ぜます。

- 5深いフライパンなどに10㎝ ほどの油を入れ、火をつけます。
- 6油が170~180度になったら、火を弱めます(油にはしを入れて泡が出る程度でOK)。


7かき揚用のおたまに材料をのせ、油に入れます。はしとスプーンを使ってもできます。


- 8キツネ色になるまで揚げ、あみに置いて油を切ります。
- 9紙をしいた器に盛り付けて完成です。塩でもめんつゆでもおいしいくいただけます。

1タマネギは薄くスライスし、ニンジンは千切りにします。ゴーヤーは縦に半分に切ってから中のわたを取り除き、薄くスライスします。

21の材料とてんぷら粉をボールに入れます。

3材料をはしでかき混ぜ、てんぷら粉を野菜全体になじませます。

43に冷水を入れ、はしで軽く混ぜます。

5深いフライパンなどに10㎝ ほどの油を入れ、火をつけます。
6油が170~180度になったら、火を弱めます(油にはしを入れて泡が出る程度でOK)。


7かき揚用のおたまに材料をのせ、油に入れます。はしとスプーンを使ってもできます。

8キツネ色になるまで揚げ、あみに置いて油を切ります。

9紙をしいた器に盛り付けて完成です。塩でもめんつゆでもおいしいくいただけます。
豚バラと大根の炒め煮

豚バラ肉は、スーパーで安売りしていることが多いので、多めに買って冷凍保存しておくのがおすすめです。大根(ダイコン)は、夏から秋にかけて大きくてみずみずしいものが出荷されます。サラダや煮物などさまざまな料理にアレンジできます。
材料(2人分)
1. 豚バラ肉: 6枚程度
2. 大根:1/4本
◆調味料
1. みりん:大さじ2
2. しょう油:大さじ2
3. 白だし:小さじ1
4. 水:100~150 cc


作り方


- 1大根をイチョウ切りにします。
- 2豚バラ肉は約5 cmに切ります。


- 3フライパンに油をひき、大根を炒めます。
- 4大根が透明になったら豚肉を加えます。


- 5豚肉に火が通ったら、調味料123を混ぜて入れます。
- 6すぐに水を入れます。


- 7軽く混ぜて煮詰めます。
- 8これくらいまで煮詰めたら完成です。

9ショウガの千切りをのせ、インゲン豆などを添えると、さらにおいしくなります。

1大根をイチョウ切りにします。

2豚バラ肉は約5 cmに切ります。

3フライパンに油をひき、大根を炒めます。

4大根が透明になったら豚肉を加えます。

5豚肉に火が通ったら、調味料123を混ぜて入れます。

6すぐに水を入れます。

7軽く混ぜて煮詰めます。

8これくらいまで煮詰めたら完成です。

9ショウガの千切りをのせ、インゲン豆などを添えると、さらにおいしくなります。
まとめ

この記事では、「ゴーヤーのかき揚げ」と「豚肉と大根の煮物」の作り方を紹介しました。どちらも安い食材で作れて栄養豊富なうえ、料理も簡単です。留学や技能実習、特定技能などで切り詰めて生活しても、体を悪くしたら元も子もありません。費用を抑えながら栄養たっぷりの料理を作り、健康で快適な日本生活を送ってください。
人気記事ランキング
-
 田んぼのタニシは食べてはいけません 31565 views
田んぼのタニシは食べてはいけません 31565 views -
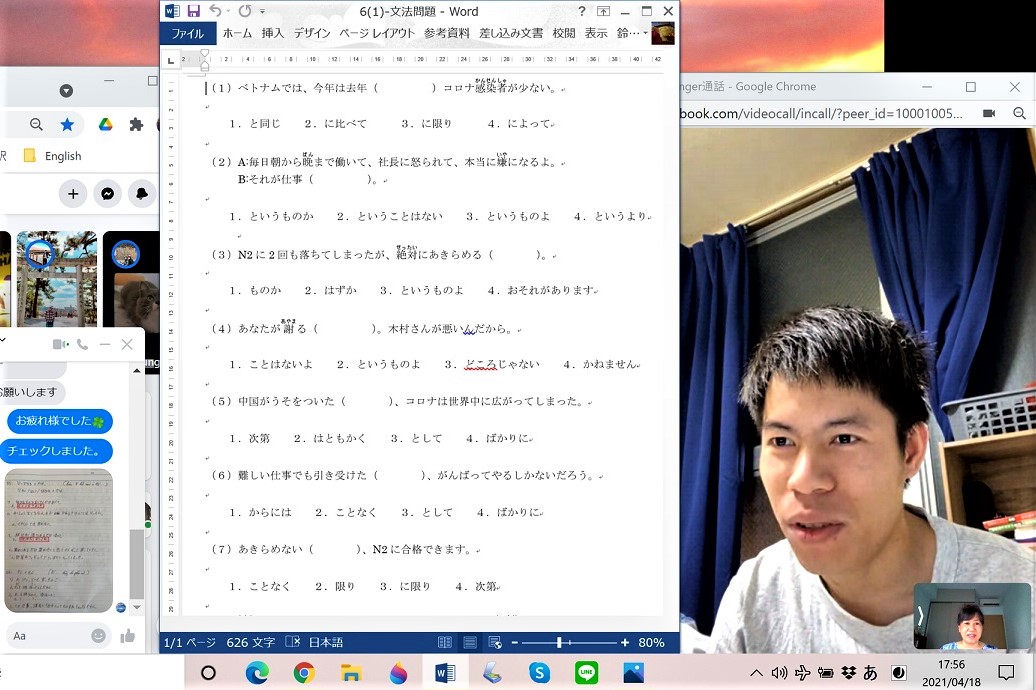 オンライン無料日本語教室 24873 views
オンライン無料日本語教室 24873 views -
 日本での「遅刻」は何分遅れから? 19713 views
日本での「遅刻」は何分遅れから? 19713 views -
 Vol. 60 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 16721 views
Vol. 60 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 16721 views -
 Vol. 42 失踪中の不法就労の様子とは 13838 views
Vol. 42 失踪中の不法就労の様子とは 13838 views
Bronze Sponsors
- 弁護士法人Global HR Strategy
- エール学園
後援
- 在ベトナム日本国大使館
- 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター
- JNTOハノイ事務所
- 関西経済連合会
- 一般社団法人 国際人流振興協会
- 公益社団法人 ベトナム協会
- NPO法人 日越ともいき支援会
協力
関連記事
-
 2025年の大きなイベント
2025年の大きなイベント2025年が始まりました。今年、日本や世界では、どのようなイベントがあるのでしょうか?これから日本に来るベトナム人やすでに日本に住んでいるベトナム人の皆さんのために、日本を中心に今年の主なイベントを紹介します。【藤田裕伸】 阪神・淡路大震災から30年(1月17日) 大震災で倒壊した高速道路=神戸市で1995年1月17日(毎日新聞社提供) 死者・行方不明者6,434人を出した阪神・淡路大震災から30年を迎えます。 大震災で倒壊した高速道路=神戸市で1995年1月17日(毎日新聞社提供) 死者・行方不明者6,434人を出した阪神・淡路大震災から30年を迎えます。 米国でトランプ大統領が就任(1月20日) 米ホワイトハウス 1月20日、トランプ米大統領が就任します。「米国ファースト」を掲げ、関税によって中国などに貿易戦争を仕かけようとしています。世界経済の悪化が懸念されています。 米ホワイトハウス 1月20日、トランプ米大統領が就任します。「米国ファースト」を掲げ、関税によって中国などに貿易戦争を仕かけようとしています。世界経済の悪化が懸念されています。 ウクライナ侵攻から3年(2月24日) ウクライナの首都キーウ ロシアがウクライナに侵攻して丸3年となります。それまでに停戦合意を実現できるのでしょうか。 ウクライナの首都キーウ ロシアがウクライナに侵攻して丸3年となります。それまでに停戦合意を実現できるのでしょうか。 中国の全人代開幕(3月5日) 2024年3月の全人代(毎日新聞社提供) 中国の全国人民代表大会(全人代)が開幕します。習近平国家主席がどのような外交政策を示すのかに注目です。 2024年3月の全人代(毎日新聞社提供) 中国の全国人民代表大会(全人代)が開幕します。習近平国家主席がどのような外交政策を示すのかに注目です。 米大リーグ開幕(3月18日) 野球の米国メジャーリーグが開幕します。大谷翔平(おおたに・しょうへい)選手が所属するドジャースと鈴木誠也(すずき・せいや)選手のカブスが東京ドームで対戦します。 野球の米国メジャーリーグが開幕します。大谷翔平(おおたに・しょうへい)選手が所属するドジャースと鈴木誠也(すずき・せいや)選手のカブスが東京ドームで対戦します。 ラジオ放送開始100年(3月22日) 日本でラジオ放送が開始されてから100年を迎えます。テレビ放送の開始はそれから28年後の1953年ですが、テレビが普及するのには時間がかかり、長きにわたり、ラジオが日本の家庭での情報収集や娯楽の主役でした。 日本でラジオ放送が開始されてから100年を迎えます。テレビ放送の開始はそれから28年後の1953年ですが、テレビが普及するのには時間がかかり、長きにわたり、ラジオが日本の家庭での情報収集や娯楽の主役でした。 大阪・関西万博が開幕(4月13日) 大阪・関西万博の候補地(毎日新聞社提供) 2025年日本国際博覧会(略称「大阪・関西万博」)が開幕します。158の国と地域が参加する予定で、閉幕は6か月後の10月13日です。 大阪・関西万博の候補地(毎日新聞社提供) 2025年日本国際博覧会(略称「大阪・関西万博」)が開幕します。158の国と地域が参加する予定で、閉幕は6か月後の10月13日です。 日航ジャンボ機墜落事故から40年(8月12日) 墜落現場で見られた航空機の主翼=事故の翌日(毎日新聞社提供) 日本航空のジャンボ機が群馬県の御巣鷹山(おすたかやま)に墜落し、520人の死者を出した事故から40年。日本の民間航空史上最悪の事故。 墜落現場で見られた航空機の主翼=事故の翌日(毎日新聞社提供) 日本航空のジャンボ機が群馬県の御巣鷹山(おすたかやま)に墜落し、520人の死者を出した事故から40年。日本の民間航空史上最悪の事故。 終戦から80年(8月15日) 昭和天皇が終戦を告げるラジオ放送に聞き入る日本国民ら=1945年8月15日撮影(毎日新聞社提供) 第二次世界大戦で日本が敗戦してから80年。さまざまな式典が行われます。 昭和天皇が終戦を告げるラジオ放送に聞き入る日本国民ら=1945年8月15日撮影(毎日新聞社提供) 第二次世界大戦で日本が敗戦してから80年。さまざまな式典が行われます。 ベトナム建国80周年(9月2日) 今のホーチミン ベトナム建国から80年。1945年9月2日に故ホー・チ・ミン主席が独立宣言を発表し、ベトナム民主共和国が成立しました。 今のホーチミン ベトナム建国から80年。1945年9月2日に故ホー・チ・ミン主席が独立宣言を発表し、ベトナム民主共和国が成立しました。
-
 2024年の大きなイベント
2024年の大きなイベント2024年が始まって半月あまり経ちました。今年、日本や世界では、どのようなイベントがあるのでしょうか?これから日本に来るベトナム人やすでに日本に住んでいるベトナム人の皆さんのために、日本を中心に今年の主なイベントを紹介します。【藤田裕伸】 東京・豊洲に観光施設(2月1日) 千客万来のHP 東京・豊洲(とよす)市場に隣接する観光施設「豊洲 千客万来(せんきゃく・ばんらい)」が開業します。 千客万来のHP 東京・豊洲(とよす)市場に隣接する観光施設「豊洲 千客万来(せんきゃく・ばんらい)」が開業します。 インドネシア大統領選挙(2月14日) ジャカルタ ベトナムの隣国インドネシアでジョコ・ウィドド大統領の後任を決める大統領選挙があります。正副大統領候補の組み合わせを国民が直接選ぶ方式で、3組のペアが立候補しています。 ジャカルタ ベトナムの隣国インドネシアでジョコ・ウィドド大統領の後任を決める大統領選挙があります。正副大統領候補の組み合わせを国民が直接選ぶ方式で、3組のペアが立候補しています。 ロシア大統領選挙(3月15日) モスクワ 通算5選を目指すプーチン大統領が無所属で出馬を決めました。プーチン氏に対抗できる有力候補はいないため、実質的な信任投票となる見通しです。 モスクワ 通算5選を目指すプーチン大統領が無所属で出馬を決めました。プーチン氏に対抗できる有力候補はいないため、実質的な信任投票となる見通しです。 北陸新幹線延伸(3月16日) 北陸新幹線が敦賀(福井県)まで延伸します。・現在の開通区間は高崎-金沢(357㎞)・金沢-敦賀(125㎞)が新たに開通 北陸新幹線が敦賀(福井県)まで延伸します。・現在の開通区間は高崎-金沢(357㎞)・金沢-敦賀(125㎞)が新たに開通 ジブリパークが全面開業(3月16日) ジブリパーク スタジオジブリの作品の世界を表現した愛知県の公園「ジブリパーク」の新エリア「魔女の谷」がオープン。 ジブリパーク スタジオジブリの作品の世界を表現した愛知県の公園「ジブリパーク」の新エリア「魔女の谷」がオープン。 米大リーグが開幕(3月20日) ドジャースタジアム 昨年、米大リーグで2度目のMVPに輝いた大谷翔平選手と、日本のプロ野球で昨年まで3年連続でMVPに選ばれた山本由伸投手(元オリックス)が今年からロサンゼルス・ドジャースで一緒にプレーします。 ドジャースタジアム 昨年、米大リーグで2度目のMVPに輝いた大谷翔平選手と、日本のプロ野球で昨年まで3年連続でMVPに選ばれた山本由伸投手(元オリックス)が今年からロサンゼルス・ドジャースで一緒にプレーします。 USJの新エリアがオープン(春ごろ) USJの公式サイト 大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)の新エリア「ドンキーコング・カントリー」がオープンします。 USJの公式サイト 大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)の新エリア「ドンキーコング・カントリー」がオープンします。 建設業と運輸業で時間外労働の上限規制(4月1日) 建設業と運送業にも他産業と同じように時間外労働の上限が設けられます。人手不足で輸送や配達が困難になる「2024年問題」が心配されています。 建設業と運送業にも他産業と同じように時間外労働の上限が設けられます。人手不足で輸送や配達が困難になる「2024年問題」が心配されています。 ディズニーシーの新エリアオープン(6月6日) 東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」がオープンします。 東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」がオープンします。 東京都知事選(7月7日) 東京都庁 東京都知事選挙の投開票が行われます。 東京都庁 東京都知事選挙の投開票が行われます。 パリ・オリンピック開幕(7月26日) フランスの首都パリでオリンピックが開幕します。 フランスの首都パリでオリンピックが開幕します。 東京科学大学が発足(10月1日) 東京工業大学と東京医科歯科大学が統合し「東京科学大学」が発足します。 東京工業大学と東京医科歯科大学が統合し「東京科学大学」が発足します。 米大統領選挙(11月5日) 米ホワイトハウス 米大統領選挙が行われます。民主党からはジョー・バイデン現大統領、共和党からはドナルド・トランプ前大統領のほか複数の人が立候補を表明しています。 米ホワイトハウス 米大統領選挙が行われます。民主党からはジョー・バイデン現大統領、共和党からはドナルド・トランプ前大統領のほか複数の人が立候補を表明しています。 健康保険証廃止(12月2日) 健康保険証が廃止され、「マイナ保険証」に移行します。マイナ保険証を持っていない人には、保険証の代わりとなる「資格確認書」が発行されます(有効期間5年)。 健康保険証が廃止され、「マイナ保険証」に移行します。マイナ保険証を持っていない人には、保険証の代わりとなる「資格確認書」が発行されます(有効期間5年)。
-
 2023年の重大(10大)ニュース
2023年の重大(10大)ニュース2023年もあと数日ですね。新型コロナが世界的に収束し、日本でもベトナムでも、マスクを外して歩く人が増えました。しかし、世界的な物価高が続き、イスラエルとパレスチナ自治区ガザ地区で武力紛争が始まるなど、波乱続きの年でした。今年の大きなニュースを振り返ります。【藤田裕伸】 1~12月 物価高と円安 ガソリン価格などへの対策について話す岸田文雄首相=2023年8月30日Ⓒ毎日新聞社 2022年から続く食品などの値上げラッシュが今年に入っても続いた。今年1年間で3万品目以上の飲食料品が値上がりした。原油やガスなどのエネルギー価格の高騰(こうとう)や、円安による原材料費の値上がりが影響した。電気代やガソリン代なども値上がりし、消費者が生活費節約のために物を買い控える動きが見られた。 ガソリン価格などへの対策について話す岸田文雄首相=2023年8月30日Ⓒ毎日新聞社 2022年から続く食品などの値上げラッシュが今年に入っても続いた。今年1年間で3万品目以上の飲食料品が値上がりした。原油やガスなどのエネルギー価格の高騰(こうとう)や、円安による原材料費の値上がりが影響した。電気代やガソリン代なども値上がりし、消費者が生活費節約のために物を買い控える動きが見られた。 3月 WBCで日本が世界一 優勝を喜ぶ日本代表チーム。トロフィーを掲げるのは大谷翔平選手=米国で2023年3月21日Ⓒ毎日新聞社 4年ごとに開催される野球のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で、日本が3大会ぶりに世界一になった。3月21日に米国で行われた決勝では、日本が米国に3―2で勝ち、日本中が喜んだ。米大リーグ・エンジェルス所属の大谷翔平選手が投手としても打者としても活躍した。 優勝を喜ぶ日本代表チーム。トロフィーを掲げるのは大谷翔平選手=米国で2023年3月21日Ⓒ毎日新聞社 4年ごとに開催される野球のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で、日本が3大会ぶりに世界一になった。3月21日に米国で行われた決勝では、日本が米国に3―2で勝ち、日本中が喜んだ。米大リーグ・エンジェルス所属の大谷翔平選手が投手としても打者としても活躍した。 4月 統一地方選挙で女性当選者が過去最多 各地の県知事や市町村長、地方議員などを選ぶ選挙が一斉に行われる「統一地方選挙」が4月にあった。88の市長選挙で過去最多の7人の女性候補が当選。道府県議の選挙でも、316人の女性が当選し、過去最多となった。ただ、日本では、議員全体に占める女性の割合はまだ少ない。 AIの利用が急拡大 文章や画像、動画、音声などを新たに作り出すことができる人工知能「生成AI」の利用が一気に広まった。米国のベンチャー企業が開発した、対話ができる「チャットGPT」などを仕事や教育で活用しようとする動きが世界中で起こっている。 文章や画像、動画、音声などを新たに作り出すことができる人工知能「生成AI」の利用が一気に広まった。米国のベンチャー企業が開発した、対話ができる「チャットGPT」などを仕事や教育で活用しようとする動きが世界中で起こっている。 5月 新型コロナ「5類感染症」に 2020年1月に日本で初めて新型コロナウイルスの感染者が確認されてから3年を超えた。今年5月に感染症法上の位置づけが「5類」に引き下げられ、感染対策は個人や企業などの判断に任されることになった。 2020年1月に日本で初めて新型コロナウイルスの感染者が確認されてから3年を超えた。今年5月に感染症法上の位置づけが「5類」に引き下げられ、感染対策は個人や企業などの判断に任されることになった。 広島でG7サミット G7=2023年5月Ⓒ毎日新聞社 広島市で5月19~21日、主要7カ国首脳会議(G7サミット)が開かれた。国際的な影響力を強める「グローバルサウス」と呼ばれる新興国・途上国など8カ国も招待され、ベトナムのファム・ミン・チン首相も出席した。最終日にはウクライナのゼレンスキー大統領も参加し、ウクライナへの支援の継続を訴えた。 G7=2023年5月Ⓒ毎日新聞社 広島市で5月19~21日、主要7カ国首脳会議(G7サミット)が開かれた。国際的な影響力を強める「グローバルサウス」と呼ばれる新興国・途上国など8カ国も招待され、ベトナムのファム・ミン・チン首相も出席した。最終日にはウクライナのゼレンスキー大統領も参加し、ウクライナへの支援の継続を訴えた。 6~8月 観測史上最も暑い夏 国連の世界気象機関などによると、今年6~8月の世界の気温は観測史上最も高かった。日本国内でも、6~8月の全国の平均気温が、気象庁の統計開始以来、最も高くなった。国連のグテレス事務総長は「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰の時代が到来した」と述べた。 国連の世界気象機関などによると、今年6~8月の世界の気温は観測史上最も高かった。日本国内でも、6~8月の全国の平均気温が、気象庁の統計開始以来、最も高くなった。国連のグテレス事務総長は「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰の時代が到来した」と述べた。 9月 ジャニーズが性加害を初めて認める 人気男性タレントを多く抱えるジャニーズ事務所は9月、亡くなったジャニー喜多川(きたがわ)元社長がタレント志望の男性多数に性加害を加えていたことを、初めて認めた。事務所は社長交代や社名変更、被害者への補償などを相次いで発表した。しかし、多数の企業が同事務所所属のタレントとのCM契約を打ち切るなど、社会の反応は厳しい。 10月 将棋の藤井聡太さんが史上初8冠 藤井聡太さん(左端)Ⓒ毎日新聞社 日本にある八つの将棋タイトルのすべてを藤井聡太さん(21)が10月11日に制覇し、最年少で史上初の「8冠」となった。将棋のタイトルを一度に複数保有することは難しく、5年前には、八つのタイトルを8人の棋士が分け合っていた。 藤井聡太さん(左端)Ⓒ毎日新聞社 日本にある八つの将棋タイトルのすべてを藤井聡太さん(21)が10月11日に制覇し、最年少で史上初の「8冠」となった。将棋のタイトルを一度に複数保有することは難しく、5年前には、八つのタイトルを8人の棋士が分け合っていた。 11~12月 自民党で裏金疑惑 自民党の中の最大派閥(グループ)である「清和(せいわ)政策研究会」(安倍派)の国会議員たちが、政治資金パーティーのチケットを販売して得た収入の一部を国に報告していなかったことがわかった。 自民党の派閥はパーティーを開催し、支持者が支払うパーティー参加費を政治資金に使っているが、参加費について国に報告することが法律で義務付けられている。しかし、安倍派はチケット販売収入の一部を国に報告せず、その分を国会議員たちに山分けしていた。お金を受け取った議員たちはこれらの金について税金も払わず、金の使途も秘密にしてきた。 このことが発覚し、安倍派の4人が大臣をやめるなど、有力議員が相次いで要職から外れる事態となった。また、12月には、東京地検が安倍派の関係事務所などを家宅捜索した。 ※役職や所属、年齢はニュース当時のもの。
-
 日本の花火
日本の花火日本の夏といえば、七夕(たなばた)やお盆休み、夏祭り、花火大会など、さまざまなイベントがあります。ベトナムと違って、日本では夏に花火大会を行います。夏の夜空を彩る大輪の花に人々が酔いしれる日本の「花火大会」。外国人が初めて日本の花火大会を見ると、花火のクオリティの高さや打ち上げ本数の多さに驚きます。この記事では、日本の夏を象徴する花火大会の楽しみ方や家で楽しむ花火などについて紹介します。 花火はなぜ「夏?」 夏に花火大会が開催されるのは日本独自の風習です。花火は16世紀以降に中国から日本に伝わり、最初は、手で持つ花火だけだったと考えられています。やがて打ち上げ花火もできましたが、花火大会は多くの場合、水辺で行われています。それはなぜでしょうか? 火事を防ぐ 花火が日本に伝わったのは16世紀以降で、江戸時代(1603~1868年)に庶民にも広まったと考えられていますが、江戸幕府(えどばくふ:日本の江戸時代の政権)は町中での花火の使用を規制しました。 それは、当時は木造建築が多いのに消防設備が不十分だったため、たくさんの建物が焼ける大火事が多かったので、火事を予防するためでした。そこで、幕府は川の近くなど水のあるところでだけ花火を許可しました。 川辺で夕涼み〈京都・鴨川〉 また、日本では昔から、夏の暑さをしのぐ手立ての一つとして、川の近くで涼(すず)む習慣があります。このようなこともあって、川や海などの水辺で花火が行われるようになりました。また、川や海のそばには人々が集まりやすい広い場所があることも、花火大会の会場に選ばれやすい理由です。 慰霊祭での花火が広まる 江戸時代の1732年、全国的な大飢饉(だいききん)が起こり、疫病(えきびょう)もはやったため、人がたくさん亡くなりました。当時の将軍・徳川吉宗(とくがわ・よしむね)は亡くなった人の霊を慰(なぐさ)めるために、江戸(えど:今の東京)の隅田川(すみだがわ)のそばで祭りを行い、その祭りの中で花火を打ち上げました。 隅田川花火大会 その後、夏の隅田川の花火は毎年恒例となり、今も引き継がれる有名な花火大会になりました。これが全国に広まり、各地で夏に花火大会が行われるきっかけになったとも言われています。 会場は早くから混みます 花火大会には有料エリアと無料エリアがあります。有料エリアで楽しみたい場合、インターネットなどで予約しなければなりません。無料エリアにはだれでも入れますが、花火がよく見える場所を確保するためには、早めに会場に行きましょう。 なにわ淀川花火大会 私が大阪市の「なにわ淀川花火大会」を見に行ったとき、開始は19時でしたが、友人のアドバイスで17時ぐらいに会場に着きました。すると、開始まで2時間もあるのに、会場にはすでにたくさんの人が来ていたので、びっくりしました。みんながいい場所を取るために早い時間から会場に来ていたのです。 また、花火大会がある日は電車が混みます。会場まで歩く人もたくさんいます。余裕をもってスケジュールを立ててください。そして、会場には大勢の人が集まりますので、会場に入る前にトイレに行っておくことをおすすめします。 花火大会で役立つ便利グッズ 花火大会に行くときには、浴衣を着る人も多いです。浴衣は借りることもできますので、「(エリア名)+浴衣レンタル」のキーワードで検索してください。 それでは、花火大会で役立つ便利グッズを紹介します。 レジャーシート 無料エリアで場所取りをするため、レジャーシートを持っていきましょう。レジャーシートは100円ショップでも買えますし、シートに座って花火を見ることができます。 手持ち扇風機、うちわ 夏なので暑いうえ、会場にはたくさんの人が集まるので、とても暑いです。手持ち扇風機やうちわで自分に風を送りましょう。うちわは日本の夏の風物詩でもあります。 モバイルバッテリー 友だちに連絡したり地図アプリを使ったりするために携帯電話が必要ですが、花火大会の動画や写真もたくさん撮るので、携帯電話の電池がなくなりがちです。あらかじめ充電していくと同時に、モバイルバッテリーも持って行くと安心ですね。 虫除け 花火大会が河川敷などで行われる場合、蚊が多いかもしれませんね。虫除けのクリームやスプレーを持って行くと安心です。 飲食品とゴミ袋 花火大会にはお弁当や飲み物を持って行くことも多いですが、ゴミ袋を持参してゴミを持ち帰るのが日本での標準的なマナーです。会場にはたいてい食べ物の屋台も出ていますが、値段が高いので、家から食べ物を持って行く人も多いです。 各地の人気の花火大会 7月〜9月の間に日本全国で花火大会が行われます。日本各地の人気の高い花火大会を紹介します。 道新・UHB花火大会(北海道) ・札幌市中心部の豊平川河川敷で開催される花火大会 ・2023年7月28日(金)19:40~ ・打ち上げ数:約4,000発 ・最寄り駅:豊水すすきの、学園前、中の島、幌平橋、中島公園 ・有料観覧席なし [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 公式サイト 仙台七夕花火大会(宮城) ・仙台市中心部で開催される花火大会 ・2023年8月5日(土)19:30~ ・打ち上げ数:16,000発 ・最寄り駅:大町西公園、泉広瀬通など ・有料観覧席あり(公式サイト参照) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 公式サイト ふくしま花火大会(福島) ・2023年7月29日(土)19:30~ ・打ち上げ数:8,000発 ・最寄り駅:JR福島駅から臨時バス(有料) ・有料観覧席あり(こちらのサイトで販売) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 公式サイト ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス(茨城) ・国営ひたち海浜公園でディズニーの音楽に合わせて花火が打ち上げられる。 ・2023年9月2日(土)18:30~ ・打ち上げ数:12,000発 ・最寄り駅:JR勝田駅からバスで海浜公園西口 ・有料観覧席あり(公式サイト参照) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 公式サイト 足立の花火大会(東京) ・東京の荒川河川敷で打ち上げ ・2023年7月22日(土)19:20~ ・打ち上げ数:約15,000発 ・最寄り駅:北千住、小菅、五反野、梅島など ・有料観覧席あり(公式サイト参照) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 公式サイト 隅田川花火大会(東京) ・最も伝統のある花火大会 ・2023年7月29日(土)19:00~ ・打ち上げ数:約20,000発 ・最寄り駅(第一会場):浅草、押上、東京スカイツリー、曳船 ・最寄り駅(第二会場):浅草、蔵前、両国、浅草橋 ・有料観覧席なし [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 公式サイト みなとみらいスマートフェスティバル(神奈川) ・横浜市の夏祭りの中で行われる花火大会 ・2023年7月31日(月)19:30~ ・打ち上げ数:約20,000発 ・最寄り駅: 横浜 ・有料観覧席あり(公式サイト参照) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 公式サイト 海の日名古屋みなと祭花火大会(愛知) ・2023年7月17日(月)19:30~ ・打ち上げ数:約3,000発 ・最寄り駅:名古屋港、築地口 ・有料観覧席なし [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 公式サイト ぎふ長良川花火大会(岐阜) ・2023年8月11日(祝)19:30~ ・打ち上げ数:非公開 ・最寄り駅: JR岐阜駅と名鉄岐阜駅から臨時バス ・有料観覧席あり(公式サイト参照) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 公式サイト びわ湖大花火大会(滋賀) ・日本最大の湖・琵琶湖の湖畔で打ち上げ ・2023年8月8日(火)19:30~ ・打ち上げ数:約10,000発 ・最寄り駅:びわ湖浜大津、大津 ・有料観覧席あり(公式サイト参照) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 公式サイト 天神祭奉納花火(大阪) ・日本3大祭りの一つ・天神祭のフィナーレを彩る花火。川に繰り出す約100隻の船団のかがり火と花火との組み合わせはここでしか見られない情緒的な景観。 ・2023年7月25日(火)日没~ ・打ち上げ数:約3,000発 ・最寄り駅: 桜ノ宮、天満橋 ・有料観覧席あり(06-6809-1588に問い合わせ) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 公式サイト なにわ淀川花火大会(大阪) ・大阪のシンボル・淀川の河川敷で打ち上げ ・2023年8月5日(土)19:30~ ・打ち上げ数:非公開 ・最寄り駅: 十三、南方、西中島南方、姫島、塚本、御幣島 ・有料観覧席あり(公式サイト参照) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 公式サイト あしだ川花火大会(広島) ・2023年8月15日(火)19:30~ ・打ち上げ数:約16,000発 ・最寄り駅: JR福山駅から臨時バス(有料) ・有料観覧席あり(公式サイト参照) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 公式サイト さかいで大橋まつり 海上花火大会(香川) ・瀬戸大橋と花火の組み合わせが美しい ・2023年8月11日(祝)20:00~ ・打ち上げ数:約15,000発 ・最寄り駅: 坂出 ・有料観覧席なし [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 公式サイト 筑後川花火大会(福岡) ・2023年8月27日(日)19:40~ ・打ち上げ数:15,000発 ・最寄り駅: JR久留米から徒歩、西鉄・久留米駅から臨時バス(有料) ・有料観覧席なし [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 公式サイト 関門海峡花火大会(福岡) ・2023年8月13日(日)19:50~ ・打ち上げ数:約15,000発 ・最寄り駅:下関。またはJR下関駅からバスで海響館前 ・有料観覧席あり(公式サイト参照) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 公式サイト あなたの住んでいる地域でどんな花火大会があるか知りたい場合は、「(エリア名)+花火大会」のキーワードで検索してみてください。 個人で楽しむ手持ち花火 日本では、個人で楽しむ手持ち花火もたくさんあります。夏になると、100円ショップやコンビニ、ディスカウントストアなどで花火が売られます。また、インターネットでも花火を買うことができます。友だちや恋人と一緒に手持ち花火を遊んでみませんか? 左からスパーク花火、線香花火、ススキ花火 ・スパーク花火(定番):雪の結晶のような細い火花が、四方八方へ飛び散る花火。火薬がむき出しで、棒に直接ぬりつけられています。 ・線香花火(定番):小さく静かに火花を散らす花火 ・ススキ花火(定番):火薬の入った紙の筒を竹棒に巻きつけた花火 線香花火 まとめ この記事では日本の夏の風物詩である花火大会と家で楽しむ小さな花火(手持ち花火)について紹介しました。 日本では毎年夏、河原や海辺などを中心に大きな花火大会が各地で行われます。花火大会には浴衣を着ていく女性も多いですが、浴衣を持っていない人もレンタル店で借りられます。 花火大会の会場は有料エリアと無料エリアに分かれている場合があります。有料エリアのチケットはインターネットなどで購入できます。無料エリアで花火大会を見る場合は、良い場所を確保するために、会場に早めに行かなければなりません。 また、日本では、個人で楽しむ手持ち花火もたくさん売られています。夏になると、100円ショップやコンビニ、ディスカウントストアなどで売られていますので、あなたも友だちと一緒に楽しんでみてはいかがですか?
人気記事ランキング
-
 田んぼのタニシは食べてはいけません 31565 views
田んぼのタニシは食べてはいけません 31565 views -
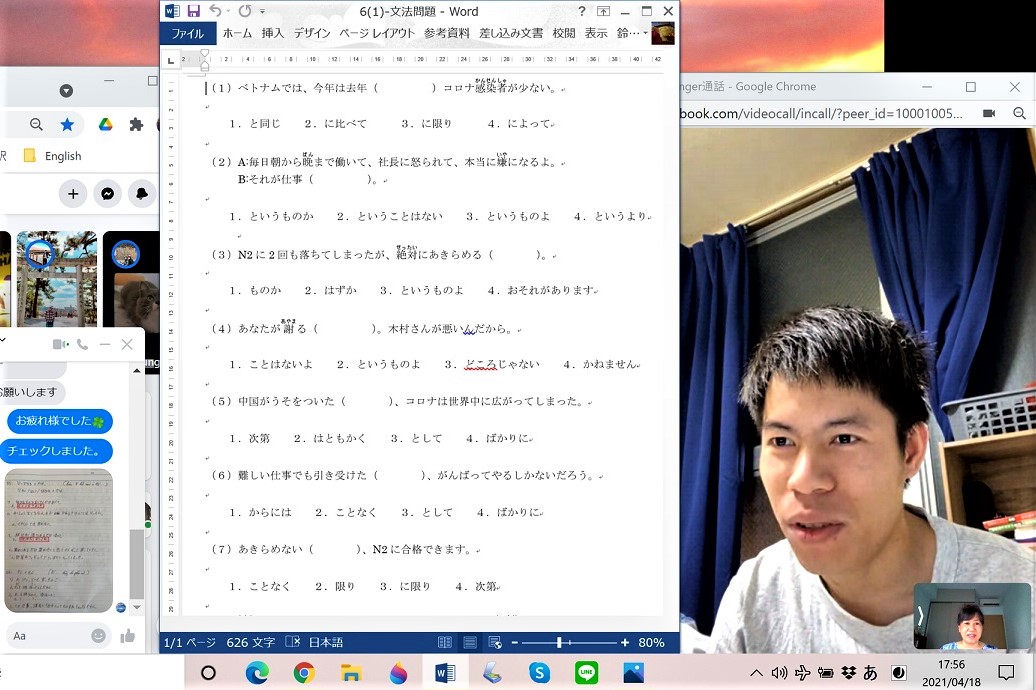 オンライン無料日本語教室 24873 views
オンライン無料日本語教室 24873 views -
 日本での「遅刻」は何分遅れから? 19713 views
日本での「遅刻」は何分遅れから? 19713 views -
 Vol. 60 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 16721 views
Vol. 60 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 16721 views -
 Vol. 42 失踪中の不法就労の様子とは 13838 views
Vol. 42 失踪中の不法就労の様子とは 13838 views
Bronze Sponsors
- 弁護士法人Global HR Strategy
- エール学園
後援
- 在ベトナム日本国大使館
- 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター
- JNTOハノイ事務所
- 関西経済連合会
- 一般社団法人 国際人流振興協会
- 公益社団法人 ベトナム協会
- NPO法人 日越ともいき支援会